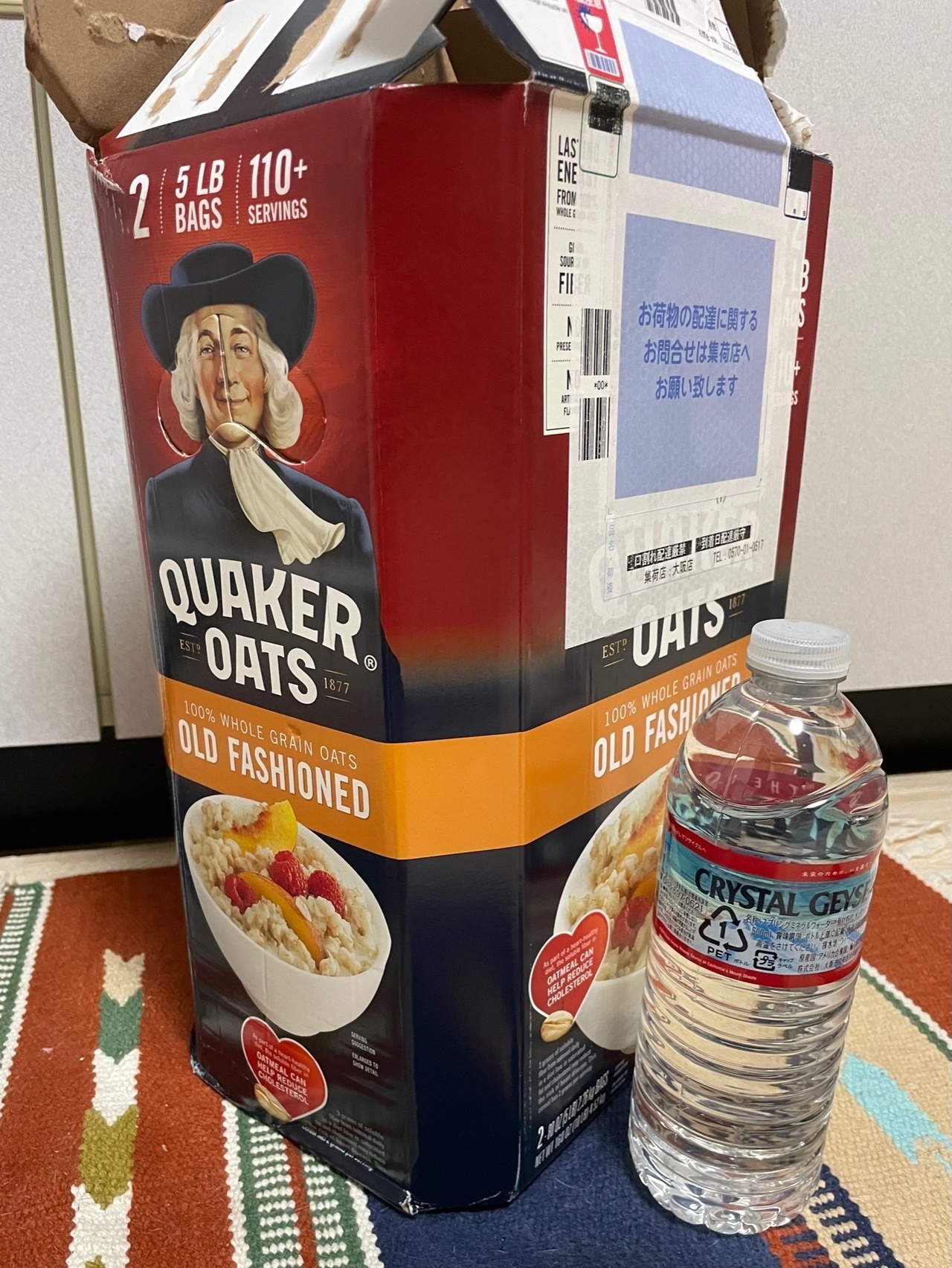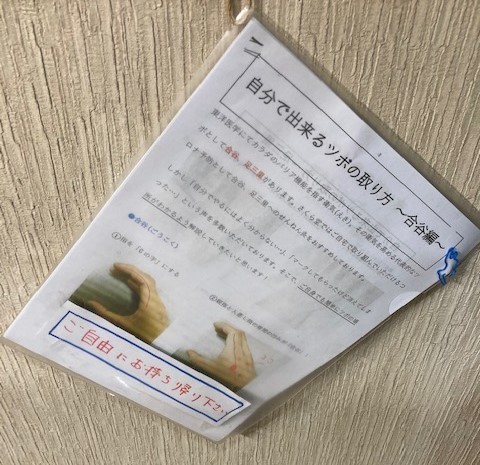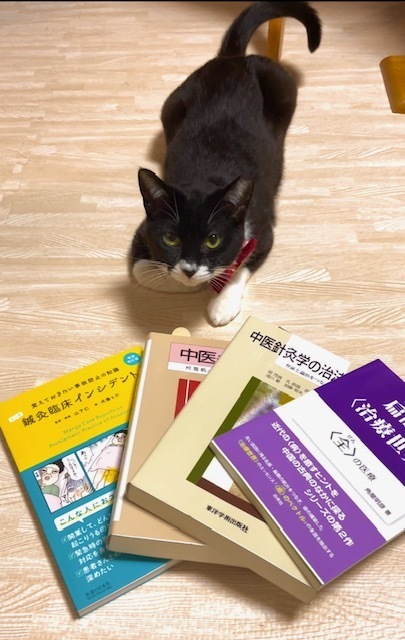家の前の空き地が一日にして二階建て一軒家の木材が組まれたので、その驚きを建設関係の知人に
話したら「一日で終わらせないと重機とかのレンタル料で割に合わなくなるんだよ。いっぱい助っ人も
いたでしょ?その人に日当出しても一日で終わらせた方が得なんだよ。」と言われました。
確かに屈強な職人さんが4〜5人で一気に組み上げていたのを思い出し、感動の裏にはそんな現実が
あったんだなぁと本質を知った研修生の大久保です。
さて、今日はそんな本質を交えてお伝えしようとする内容が「オーツ麦」です。
最近の健康ブームで何かと話題になっているのですが、間違った食べ方をして健康被害も多々あるよう
なので、東洋医学を交えてお伝え致します。
まず、このオーツ麦ですが、イネ科の穀物で別名を「燕麦(えんばく)」「オートミール」「オート麦」
「オート」と呼びます。皆さんが聞き馴染みのあるものだと「グラノーラ」も元々はこのオーツ麦を
加工しているものです。これが何故話題になっているのかというと、玄米より食物繊維やたんぱく質、
ビタミンが豊富で少量でもお腹を満たせるのでダイエット食として注目を集めています。
食べ方はシリアル食品のように牛乳をかけたり、レンジでふっくらパンのようにしたり、お粥のように
煮たりと色々とアレンジができて毎日でも食べられるようなのですが、調べてみると「げっぷが出る」
「便秘になる」「肌荒れする」「浮腫む」などの悪影響があるようなので、中医学を交えながら
ご説明致します。
ではまずオーツ麦の効能から見てみましょう。
四気五味 :甘味 平属性
帰経 :脾胃
効果 :活血理気 補益脾胃 滑ちょう催産 降胆固醇 益肝和胃 潤腸通便
何となく分かりますか?漢字を使う日本に生まれて良かったと思える瞬間ですね(笑)
大まかに説明しますと、オーツ麦は温にも寒にも属さず、脾胃を調整し、便通を良くするとなります。
また、「降胆固醇」とはコレステロールを下げるという事で、「催産」とは難産の際に食べる事で
分娩を促す作用があると中国の古典『本草綱目(ほんぞうこうもく)』に記載されています。
「こんなに良いことばかりなのに何で悪影響が出るの?」
と、思いますよね!これは食べ方に問題があるのだと考えられます。
ただでさえ穀物で消化に時間がかかる食べ物なのに、冷たい牛乳や三食全てをオーツ麦にしてしまったら
胃から腸に流れず滞ってしまう『食滞』が起きます。そうなってしまったら胃の気が逆流して『げっぷ』
が起きますし、たとえ流れたとしてもその後の食物の流れを遅くしてしまい『便秘』になります。
また、冷たいものと一緒に摂ることで脾の陽気を不足させたり、傷つけてしまえば湿や痰が生じ、
『肌荒れ』『浮腫み』が出たり、逆に体重が増加する可能性もあります。
いかがだったでしょうか?ちょっと面倒ではありますが、本質を調べると色々な事が分かって、何に
気を付ければ良いのかが分かると思います。「コロナで運動できないから食べ物で痩せるっ!」と
お考えの方はご参考にしてみてください。
我が家の4.5kgオーツ麦
研修生 大久保昌哉
※新着時期を過ぎると左サイドバー《みんなのブログ》に収められています。