こんにちは。研修生の大久保です。
前回に引き続き「昭和鍼灸の歳月」のご紹介をしていこうと思います。
本書は三部構成となっており、恐縮ながら題名の後に私なりのサブタイトルを付けると…
第一部『古典に還れ』 経絡“的”治療の誕生前夜
第二部『病は経絡によって発す』 経絡治療の確立と普及
第三部『柳谷先生と竹山先生』 キーマンの人柄
となっております。
〇第一部『古典に還れ』
始まりは大正十一年に十六歳の柳谷素霊少年が北海道から現在の渋谷区にあった日本鍼灸専門学院の門をくぐる所から始まります。鍼灸業界では大正七年に制定された「改正孔穴」により弾圧真っただ中の入学です。
「改正孔穴」とは、当時380穴ほどあった経穴(現在は361穴)を120穴に省略し、さらに経穴の取り方も変更したため、古来より語り継がれてきた治療とは言えなくなってしまいました。
この「改正孔穴」により、多くの鍼灸師は学校を卒業しても効果的な治療ができないでいました。そこで柳谷素霊(敬称略)は地方で受け継がれている治療法や中国から伝わる医書を基に臨床の場で試行錯誤します。時代は大正から昭和に代わり、この頃に出会った八木下勝之助によって経絡的治療は大きく発展していきます。また、岡部素道や井上恵理(けいり)などが現れ、経絡治療の前身である経絡“的”治療が少しずつ形作られていきます。
〇第二部『病は経絡によって発す』
第二部は竹山晋一朗にスポットが当てられます。竹山は新聞記者の時に医者から見放されるほど体調を崩し、それを東洋医学によって救われた事で鍼灸界に入り、経絡治療普及の先頭を走ります。その後、頭角を現した竹山は岡部宅での議論の場で『(経絡的治療の)「的」はあっても無くてもいいので取ってしまえ』という鶴の一声によって現在の経絡治療と正式に呼ばれるようになりました。
〇第三部『柳谷先生と竹山先生』
第三部は秀才で努力家な柳谷素霊と豪快な竹山晋一朗のエピソードです。一見相対しそうな二人ですがどちらもお酒が好きで、真冬に酔っぱらって側溝に落ちてびしょ濡れになったり、口論の末心臓に鍼を刺したりと、前半で描かれている両氏の偉大な功績がある分、人間味のある一面が垣間見えました。
〇読み終えて…
戦後75年間で色々なものが生まれ整備されてゆきましたが、鍼灸界においても経絡治療という数ある治療法の一つの歴史を知れた事は、直感的に動き、あまり時代背景など周りの事に興味を示さない私にとって、とても勉強になりました。また、本書では度々先生方の口論する場面が描かれているのですが、本気で鍼灸の事を考えているからこそで、羨ましくも思えました。私もコロナ禍が落ち着き、以前のように勉強会の後の飲み会ができるようになる頃には熱い治療論が話せるよう、より一層精進しなくてはと思う一冊となりました。
研修生 大久保昌哉
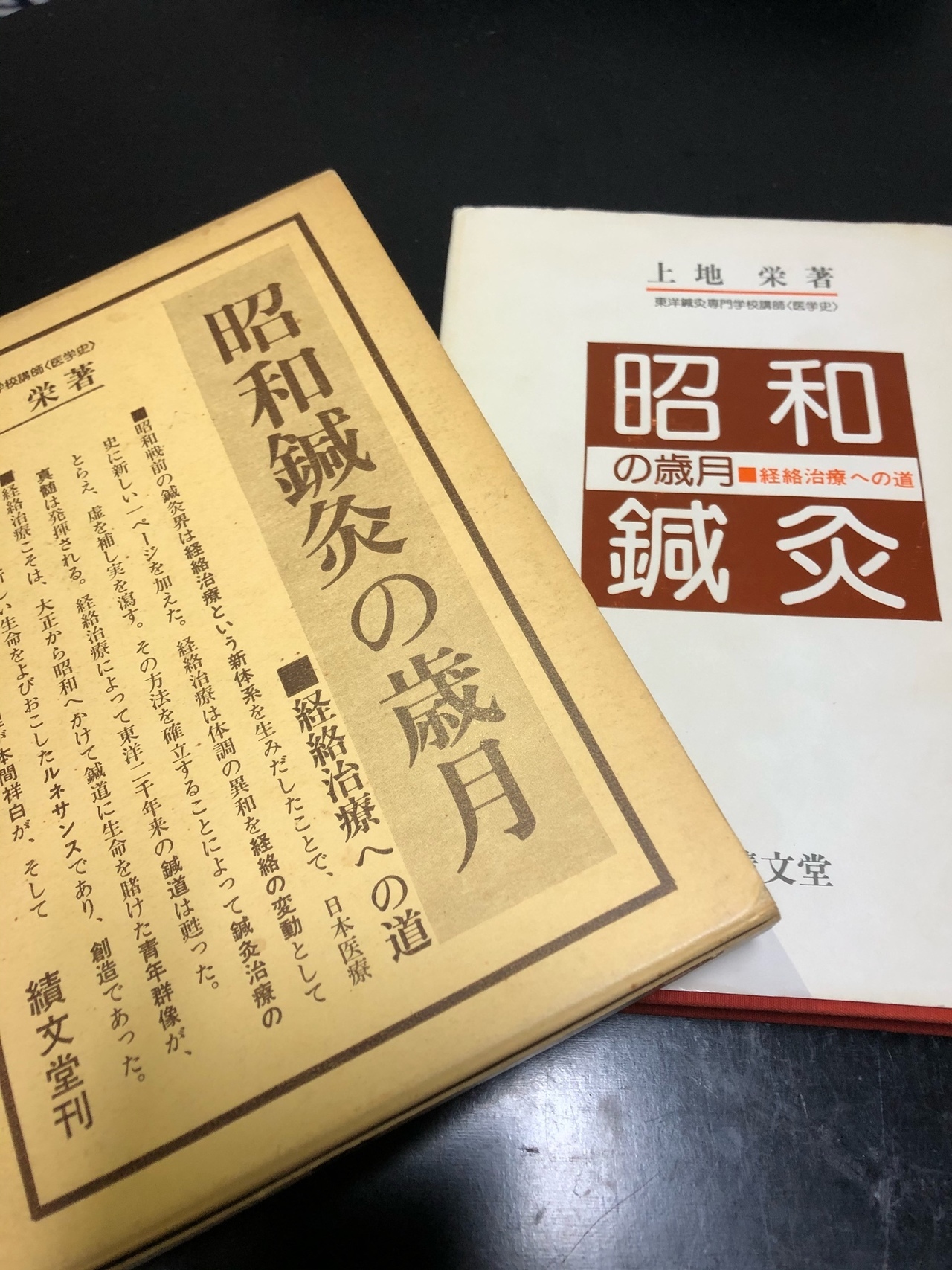
※新着時期を過ぎると左サイドバー《みんなのブログ》に収められています。
