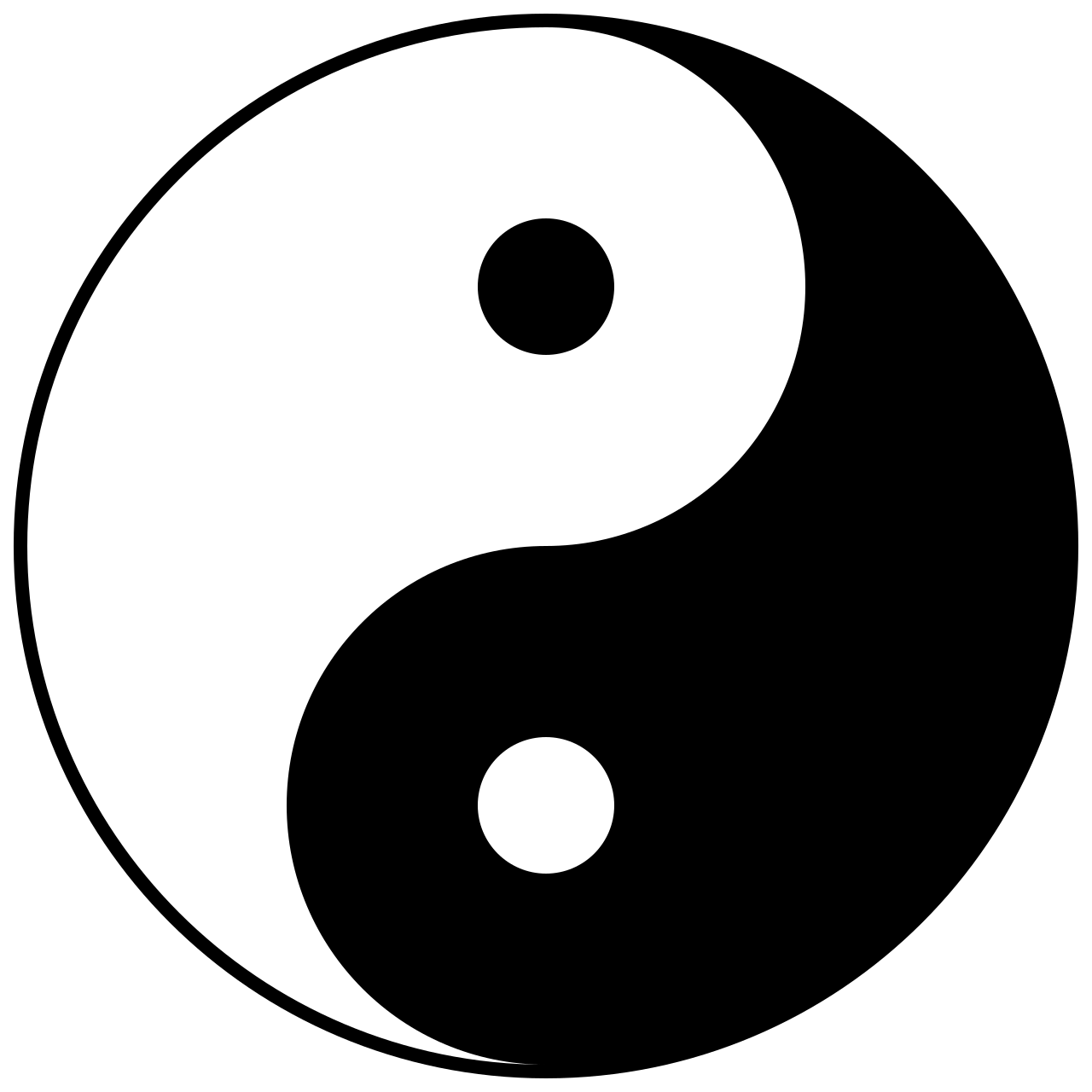コロナの影響か毎日の生活を見直すようになった。
結果、今周りにいる人とのかかわりを大切にすることや日常生活の見直しなど毎日を丁寧に暮らそうと感じている。
その中で一人でできることとして「食事」・「運動」・「睡眠」が何より大切なんだなぁ、としみじみと感じている。そして「食事」は日常生活における楽しみのかなりのウエイトを占める。
いくつになっても「おいしく食べれること」は人間にとって何よりも大切なのだなと感じている。
「予防歯科」という概念があるが、自分も「歯」は今のうちから守っていきたい。
前置きが長くなってしまったが、今回は「牙歯浮動」について解説していきたい。
もちろん「歯」のトラブルについても鍼灸治療は対応している。
●口腔内における東洋医学的な基礎概念
①「歯」は口腔内にあって食物を咀嚼する器官とされている。
古典上に「腎は骨を主る」「骨は歯の余たり」という記載もあり、歯の成長過程や堅固かどうかは五臓の「腎」に密接に関連している。
②「ギン」は歯根周囲の組織、いわば歯肉を指す。
これらは上歯ギン・下歯ギンに分けられる。これらは東洋医学上の気血(エネルギーや栄養物質)の通り道である経絡が各々通っているとされている。
上歯ギンは「足の陽明胃経」(六腑の「胃」)と密接に関係している。
下歯ギンは「手の陽明大腸経」(六腑「大腸」)と密接に関連している。
追加情報としては、これらの陽明経は他の経絡の中でも特に「気血」の量が豊富といわれている。
●「歯がグラグラする(牙歯揺動)」の東洋医学的解説
先に論じた通り、歯や歯肉は五臓の「腎」・六腑の「胃」「大腸」と密接にかかわっている。
ゆえに歯の疾患の多くは「腎」「胃」「大腸」のトラブルで見られることが多い。
以下、大きく3つの原因に分けてみたので解説をしたいと思う。
①陽明(胃・大腸)熱タイプ
歯肉に通ずる経絡(気血運行ルート)に熱が入ることが原因となる。
主に飲酒や油濃いもの・辛いものの食べ過ぎにより生じる。胃・大腸などの消化器に熱が生じるために身体各部に熱症状が生じる。
(特徴)
熱気をおびているために歯肉が赤く腫れる・歯が揺れ動く(歯肉を養う栄養分・歯をホールドするエネルギーが熱により焼却されるため)
(身体症状)
口臭(胃⇒口へ熱が昇るため)・便秘(便の水分が焼却されるため)・舌が赤い(体内に熱が生じているため)
②腎陰虚タイプ
「腎」における陰分の虚損が原因になる。歯を構成する物質が不足していることが歯がグラグラするという事態を招く。青壮年に多くみられ、過労や過剰な性生活が原因となることが多い。
陰分は身体を養い、潤す役割を有している。不足することで栄養不足・微弱な熱症状が全身で見られる。
(特徴)
歯がグラグラする(歯構成物質が不足するため)
(身体症状)
頭がクラクラする・髪が抜ける(頭部が養われないため)・脈が細い(栄養不足のため)
手足・胸部のほてり感(熱を有しているため)
③腎気虚タイプ
気の作用の一つとして、固摂作用がある。これは物を一定位置にとどめておく作用を有する。
歯と密接に関連する「腎」における固摂のエネルギーの失調は歯のグラグラ感を生じさせる。
加齢や過労が原因となることが多い。固摂エネルギーに限らず、身体のエネルギー不足症状が全身に現れる。
(特徴)
歯がグラグラする(一定位置に保持する力が低下するため)
(身体症状)
尿漏れ(膀胱内に尿をとどめておく力が不足するため)・脈が弱弱しい(全身のエネルギーが少ないため)
8020運動という言葉がありますが、お口の中は大切に!
スタッフ 杉本