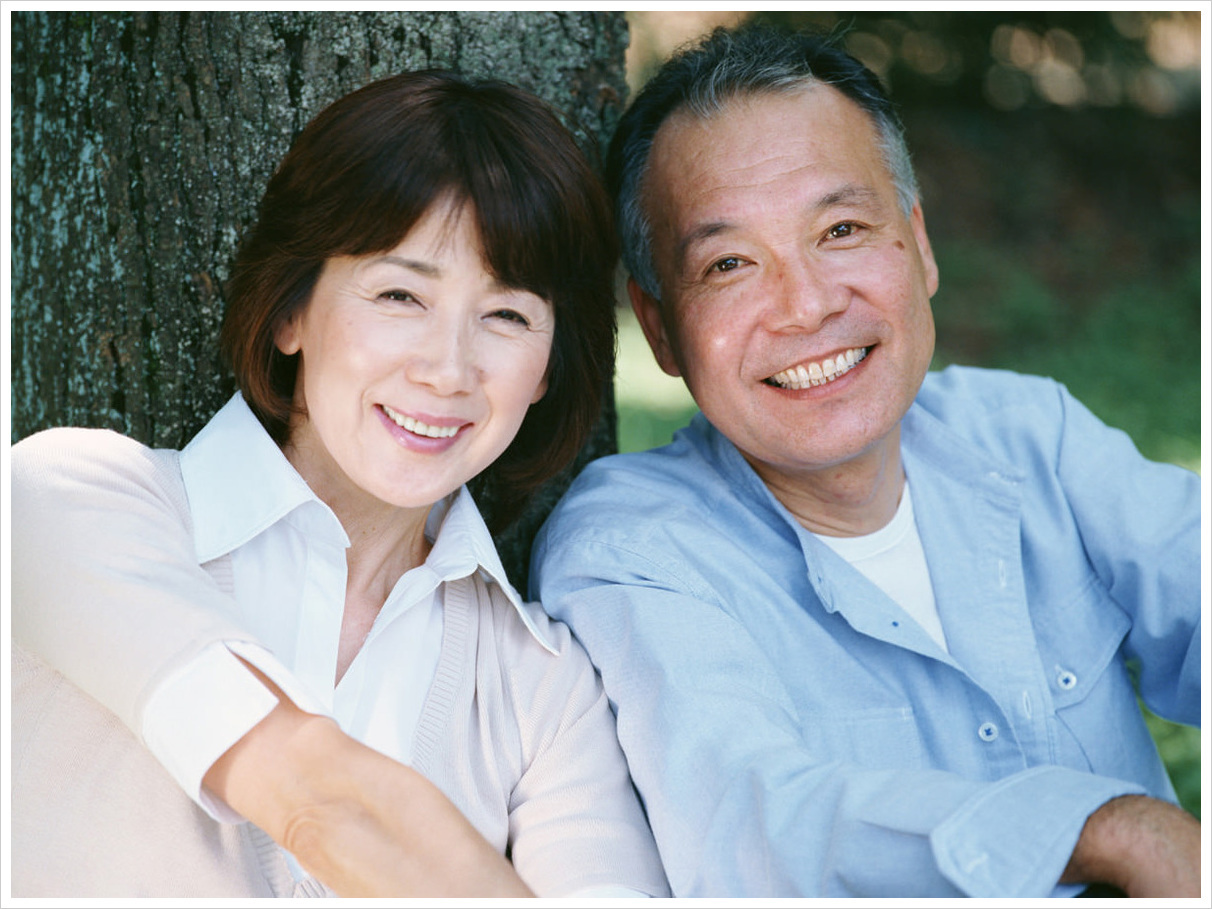2020/5
◆因果は続く
現代医学の特徴のひとつは原因論にあります。
原因論は文字通りこの病気の原因はどこにあるのか?を探します。もちろん、その原因を対応する治療をするためにです。つまりその公式は「原因を解消する=その疾患が治る」です。
私たちはその公式を当然のこととして受け止めています。
しかし、考えてみると、これは意外な盲点もあります。
現象には必ずそれを起こす原因があります。その原因もまた現象です。その現象にも原因があります。それもまたもや現象です。きりがありません。
たとえば交通渋滞の原因は何か?ー車を生産するメーカが原因だー車が増えた原因は何か?−車の走りやすい道路をたくさん作ったからーたくさん道路を作った原因はー道路公団の仕事がなくなると困るから・・・きりがないのです。
もちろん原因はひとつではありませんー渋滞の原因はー信号が多すぎるからーなぜ信号が多いのかー正確な信号を作れるメーカが存在するから・・・延々と続きます。
因果というのは常に連続性の中で続くという性質があるのです。
医学の場合はどこで線引きをするのか?という問題が出てきます。
おおよそわかる範囲に限定させます。人知の及ぶ範囲で切ります。
科学技術の発達は日進月歩です。
つまり現代は容易にさらに進んだ原因が解明されることになります。しかし、それを踏まえての治療学ですから、そこには必ずタイムラグが出来ます。
そこで、病名は細分化した(病名が増える)のに、薬が同じなどということが起こり得るわけです。
あまり穴を掘り過ぎて、周りの土砂を崩すこともあります。
私は料理を作りますが、玉ねぎのみじん切りは包丁とまな板が一番早いのです。便利そうに見えるみじん切りを作る器具は、結局洗ったりしなけばならないので労力がかかります。
人の叡智は、数々の病気の原因を特定しましたが、病人の総数が減っていないことも事実でしょう。
有機体としての調和から外れた原因の追及には若干の疑問を感じてしまうこの頃です。