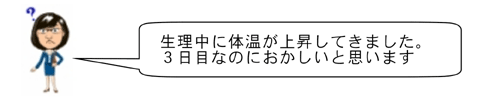
■ 《単発か連続か》 体温はもともとよく上下するものです。患者さんの話をまとめると、一過性で、かつ0.2〜0.3程度の上昇なら、原因の特定は難しいようです。もちろん、黄帯ホルモンの萎縮不全や子宮内膜の炎症などによるケースもあります。
また貝原益軒の養生訓だった?と思いますが、「生理中は洗髪するな」的な下りがあります。つまり生理中は体外に気血が出てしまうので、今風にいうなら免疫力が落ち、風邪を引きやすくなります。つまり感冒の可能性も考えられます。 感冒はその後の病状から、割と判断がつきやすいのではないでしょうか。
黄体ホルモンは体温上昇と絡んできます。黄体形成不全なら高温期の上がりが悪くなり、逆に萎縮不全なら生理になっても高温期だったり、生理中に再度上がったりします。
まずはホルモン値の検査が必要だと思います。東洋医学では圧倒的に血オのケースに見られます。よく使うツボが血海、地機、次膠などです。
子宮内膜症の場合、炎症のレベルにもよりますが、ときにサイトカインという物質を放出するため、体温が上がることがあります。
病院に行く途中にでも親指と人さし指の水掻きのへこみにある手の合谷というツボを持続的(2分ほど)にギュッと押しから行ってください。
しかし、定期的にそうである場合を除き、一過性の体温上昇なら、「微妙な体調変化」というごく日常的な文脈の範囲で考えるのが無難でしょう。
■ 《単発はリラックス》
いずれにせよ、気にしすぎると、かえってその状態を無意識に作り出すこともあります。基礎体温を気にし過ぎ、「上がったらどうしよう」と不安や緊張状態でその日を迎えたら、かえって上がりやすくなります。
中医学では、肝気鬱による鬱熱といって、極度の緊張状態で気が停滞すると、熱を帯びてきます。
【人の体は動的平衡状態を保とうとする】という原則からも、リラックスすることです。ただし「リラックスしてください」ということは、どこの病院に行っても言われますよね。ちょっと芸がありません。
リラックスとは余分な力が入っていない状態です。
ふたつの視点があります。ひとつは意識を外の別な世界に持ってゆきます。
つまり目下の悩みごとから意識的に心を離します。つまり悩んでいられない環境を設定してしまいます。
ふたつめはそのことを意識しながら、呼吸などを整え、筋肉を弛緩させてゆきます。静かに頭で悩みごとを考えながらも、筋肉が弛緩してゆく様を味わいます。さっきとは逆に内に意識を持ってゆきます。
ひとそれぞれやり方はあるでしょうが、内外どちらかの方法で試してみてはいかがでしょうか。
