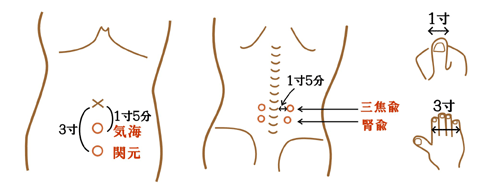確かに高温相が10日以下だと心配です。加えて低温相と高温相の差が0.3度以内、排卵後の体温上昇がダラダラとしか上がらないなら、黄体機能不全あたりを考えるのが一般です。
黄体は排卵を契機に卵胞が変化したもので、その黄体からは黄体ホルモンが出ます。黄体ホルモンには3つの働きがあります。
①体温上昇の維持
②子宮内膜を厚くする
③子宮収縮の抑制
《鍼灸で子宮の気を増加させる》
この黄体ホルモンの働きを東洋医学に置き換えると、子宮内の気の働きに相当します(それだけではありませんが・・・)。
○体温上昇は、子宮内の躍動性の高さの表現、あるいは気の温煦作用(気の6大作用のひとつ;温める働き)によるものです。
○子宮収縮の抑制は流産を防ぐためです。これは気の固摂作用(固定し落ちなくする働き)によります。
ここまでを要約すると、子宮に気を送り込む働きが弱いと、黄体の機能不全になりやすいということがわかります。このようなときは関元や気海、腎兪、三焦兪というツボが有効です。
また、肝気鬱(かんきうつ)といって全身の気の流れが悪い状態では、子宮への気の流入が減ることもあります。生理周期が乱れる、胸の張りがいつもに増して強い、ひどいときには一過性の高プロラクチン血症などを起こします。またLHサージを早めに起こしてしまうこともあるので未成熟状態で排卵したり、逆に排卵には時期尚早となり遺残卵胞となることもあります。 あるいは長期の疲労状態や睡眠不足などでは、全身の気の不足が予想されます。当然ながら子宮に回す分の気が少なくなります。 そこで問診はもとより、脈や舌あるいはお腹の状態で、まず全身の状態を把握します。
つぎに子宮との関連を考慮します。
そして最終的には子宮の気を増加させるような鍼灸治療をしてゆくという手順となります。