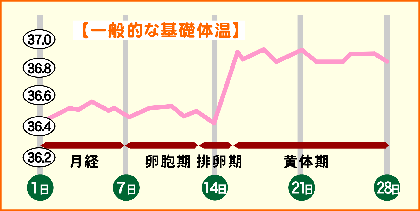2020/9
兼ねてより不妊外来に通う方の心持ちが気になっていました。
当院でも、定期的鍼灸治療を受けられる方~移植や採卵前後に集中して来られる方までを含めると実に不妊外来と併用する方が9割以上に上ります。
不妊外来には元々妊娠しにくい、あるいはご結婚が高年齢だという理由で門を叩いたはず。
少なからず子供が授かりにくいということがきっかけであったと思います。
ならば「不妊外来に通っても妊娠にくいことに変わりはないのですが、自然よりその妊娠確率が上がる」ということが真相であり、きつい言い方ではありますが、9割強の方が妊娠に至るということではありません。
ときおりおられるのですが、「一回一回が勝負だ」という気持ちが強すぎて、神経をする減らしてしまう方がいます。
不妊治療が他の治療と決定的に異なる点は、ドクター、患者さんの双方がゴール(妊娠)を設定出来ないというところにあります。
100メートル走のように全力疾走するか、マラソンのようにペース配分を考え走るかが読めないということです。
1回の体外で終了なら全力疾走しても良いのですが、マラソンで全力疾走してしまうと体も心も持ちません。
妊娠のためにやれることはご自身の生活の範囲でやりながら、決して生活のすべてをそこにかけないような態度が肝要かと思います。
これには年齢を問いません。必要以上の焦りは脳下垂体ー視床下部系のホルモンを乱し、妊娠に不利な状況を作り上げるためです。
僭越ながら、半歩ほど引いた、ちょうど中距離走のランナーような心持が大事だと思います。
他の楽しみを忘れるようなら《焦っている》ということですね。
※新着時期を過ぎると左サイドバー《不妊症のガイドライン》に収められています。